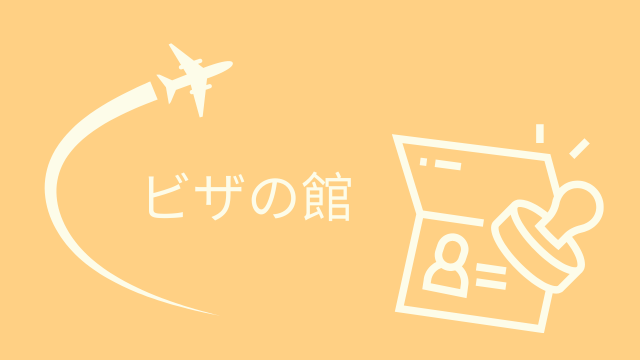前回の章では、筆者であるロバート氏が「現代人にとっての幽霊」と呼ぶ科学の法則の話を取り上げました。実際の本の内容では展開していくストーリーの順序が少し違うのですが、彼の思考を理解するという面においては、ここを出発点としても面白いのではないかなと考えています。
さて、「全ては人間の心の中に存在しているに過ぎない」という一聞すると突拍子もないような主張に聞こえるこの考えは、筆者自身、他人からの「借り物」だと告白しています。それはパイドロスという人物が考えていたことの一つだと。。。ここでもう1人の人物「パイドロス」という人間について少しだけ言及しておく必要があります。パイドロスとは、もう1人の筆者・正確にはロバート氏のかつての人格です。物語を読み進めていくうちに次第に明らかになっていくのですが、筆者はかつて精神異常をきたし脳に電流を流すECT治療法によって一度人格を失っています。本人曰く、頭に電流器が取り付けらる前「(この頃) パイドロス(=自分) は、裁判所の司令によってお金、財産、子供たち、市民としての権利でさえも、ありとあらゆる所有物全てを失った」と述べています。このパイドロスが人格を失うまでの過程それ自体も非常に長い話で興味深いものですので、少し後に回して紹介したいと思います。しかし、ここではまずこのパイドロスの思考に慣れるため「全ては人間の心の中にある」という話をもう少し深掘りしていくことにしましょう。
筆者はこう言います。人類が考え得る思考の抽象度や難易度を山に例えたならば、パイドロスの思考は「精神の高地」で体系化されていったものであると。この精神の高地では、登る山が高くなればなるほど登山者が薄い空気に慣れていかなければならないのと同様に、どんどん抽象度が上がっていく曖昧な思考過程に加え、「真理とは何か?、また真理があるならばをそれをどのように知ることができるのか?」、「私たちはどのようにして物事を認識するのか?、認識する「私」という「魂」が存在するのか、それとも単にこの魂は、知覚を統合する細胞が集まったものにすぎないのか?」といったようなとてつもなくスケールの大きな問いに対する質問やその答えに精神を慣らしていく必要があるようです。そこでロバート氏は言いました。パイドロスの思考について知るには、この「精神の高地」において現代史におけるの登山者の中でも最高クラスの1人として名を馳せたドイツの哲学者: エマニュエル・カントの思想と、パイドロスがそれについてどのように考えていたのかについて知っておいてほしいと。。。
デイヴィッド・ヒュームとエマニュエル・カント
このような形でカントが紹介されていき、まずカントを知るにはヒュームという人物の思想から始めなければならない、、、と続いていきます。この偉大な哲学者2名の超論理的な論証の展開は非常に面白いので順番にここで取り上げていきます。「18世紀を代表する哲学者にして近代哲学の祖」といわれるカント氏の論証に浸り、ロバート氏が言うように今後のパイドロスの思想への準備運動としてみることにしましょう。
日本語翻訳はこちらから
David Hume’s Reasoning
To follow Kant one must also understand something about the Scottish philosopher David Hume.
Hume had previously submitted that if one follows the strictest rules of logical induction and deduction from experience to determine the true nature of the world, one must arrive at certain conclusions.
His reasoning followed lines that would result from answers to this question: Suppose a child is born devoid of all senses; he has no sight, no hearing, no touch, no smell, no taste…nothing. There’s no way whatsoever for him to receive any sensations from the outside world. And suppose this child is fed intravenously and otherwise attended to and kept alive for eighteen years in this state of existence. The question is then asked: Does this eighteen-year-old person have a thought in his head? If so, where does it come from? How does he get it?
Hume would have answered that the eighteen-year-old had no thoughts whatsoever, and in giving this answer would have defined himself as an empiricist, one who believes all knowledge is derived exclusively from the senses. The scientific method of experimentation is carefully controlled empiricism. Common sense today is empiricism, since an overwhelming majority would agree with Hume, even though in other cultures and other times a majority might have differed.
The first problem of empiricism, if empiricism is believed, concerns the nature of “substance.” If all our knowledge comes from sensory data, what exactly is this substance which is supposed to give off the sensory data itself? If you try to imagine what this substance is, apart from what is sensed, you’ll find yourself thinking about nothing whatsoever.
Since all knowledge comes from sensory impressions and since there’s no sensory impression of substance itself, it follows logically that there is no knowledge of substance. It’s just something we imagine. It’s entirely within our own minds. The idea that there’s something out there giving off the properties we perceive is just another of those common-sense notions similar to the common-sense notion children have that the earth is flat and parallel lines never meet.Secondly, if one starts with the premise that all our knowledge comes to us through our senses, one must ask, From what sense data is our knowledge of causation received? In other words, what is the scientific empirical basis of causation itself?
Hume’s answer is “None.” There’s no evidence for causation in our sensations. Like substance, it’s just something we imagine when one thing repeatedly follows another. It has no real existence in the world we observe. If one accepts the premise that all knowledge comes to us through our senses, Hume says, then one must logically conclude that both “Nature” and “Nature’s laws” are creations of our own imagination.This idea that the entire world is within one’s own mind could be dismissed as absurd if Hume had just thrown it out for speculation. But he was making it an airtight case.
日本語翻訳はこちらから
以下、かなり個人的な見解になりますのでご了承ください。
あえて先に忠告させて頂くことがあるとすれば「この高次元の思考について来れない人は読んでもらわなくて結構」と言わんばかりに読者を突き放す難解な部分が多々あります。この本の感想を書いているブログ等もいくつか見かけましたが、相当な学歴をお持ちの方でも「哲学的な部分は何が言いたいのか分からなかった。なぜそんなことを気に掛ける必要があるのか不明。」などといった考察が多く、未だにパーシグ氏の考えの核心を捉えていると思える考察が少ないのが現状です。ただ、一つ言えるのは、日本だけでなく世界中で「この本を読んで物事に関する考え方が180°変わった。」と言う人は少なくありません。僕もその1人です。それほどに多くの人の心に響き、人の奥底に眠る深い思考を目覚めさせてくれる一冊だと思います。